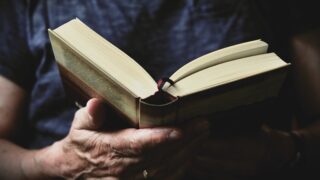 ブログ
ブログ 『福音派 ー終末論に引き裂かれるアメリカ社会 加藤喜之』から考えた物語に取り込まれること
唐突ですが、私はアメリカ社会というものをあまり理解していませんでした。というのも『福音派 ー終末論に引き裂かれるアメリカ社会 加藤喜之』という方を読むまでは。この本を読むと「アメリカという社会がどういう社会であるのか」ということが理解できま...
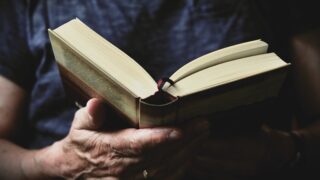 ブログ
ブログ 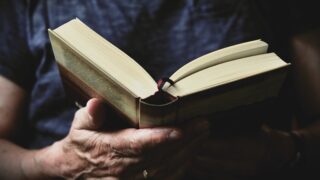 ブログ
ブログ  本
本  ブログ
ブログ  ブログ
ブログ  チャレンジ報告
チャレンジ報告  ブログ
ブログ  ブログ
ブログ  ブログ
ブログ  ブログ
ブログ