今回知の巨人と呼ばれるスティーブンピンカーの『21世紀の啓蒙』という本を読みました。
今回は、この本を読んだ内容の話ではなく、私が感じた違和感から、
本を読むことに潜む怖さを感じそこから、
読書って読者の力量も必要なのかもしれないと感じたこと、
について書いてみようと思います。
この本の私のさっとした感想
この本は基本的には非常に気持ちが前向きになるような内容が書かれていました。
単純にまとめれば、今が一番良い状態で、これからさらに良くなる、というような内容です。
それらがデータ、数値を元にしながら書かれています。
だからこそ、感覚的な話ではなく、より信用できるというか、納得感を持って読むことが
できたように思います。
(根拠もなく、これからはさらに良くなると言われても納得感は得られませんものね。)
そして、これからも、私たちは、理性、科学、ヒューマニズムを持ってして、進歩できるのだ
ということが書かれていました。
毎日暗いニュースしか見ていないから、非常に希望が持てるような気がします。
この感想はおおよそ、この本を読んで多くの人が感じるであろう感想になるのではないかと思います。
筆者も「科学」ということに重点を置いていますので、それに則って、
データを示して説明してくれているので当たり前と言えば当たり前なのかもしれません。
これからは私が感じた違和感から、そこから着想したことについて書いてみようと思います。
私が感じた違和感
先ほども書きましたが、この本は全体として希望の持てる良書であると感じます。
しかし、私が違和感を感じたのは、最後の章ヒューマニズムを改めて擁護するという章です。
そこには「ニーチェ」のこと、「イスラム教」のことが書かれていました。
それらを読んでいたら、著者の考えに偏りがあるのではないかという違和感を感じました。
「ニーチェ」に関しての違和感
例えば、「ニーチェ」について書かれている部分。この部分を読んで私が抱いた率直な印象は、
ピンカーは「ニーチェ」をファシズムを扇動するような思想家だと表現したがっている
ということでした。
ニーチェが書いた文章をいくつか挙げて、書かれていました。その引用の一部を以下に記すと
「高次の人間」は対手に対して宣戦布告すべきだ。(中略)人間の改良に役立つような、すなわち強い者をより強くし、世を儚む者どもを無力化して破壊するような厳しい教えが必要だ。「道徳」と呼ばれる戯言を消し去ること。489
この部分を読むとどうでしょうか?
確かに、ファシズム的であったり、何か差別的な発言のようにも感じます。
ですが、「ニーチェ」ってそんな思想だったっけ?と私は感じました。
以前ニーチェに関する本とかそれに関連する本を読んだような気がして、
その時の印象と全く異なったからです。
また著者曰く、ニーチェの妹が熱心なナチズム信仰があったとか。そのような書かれ方をすると
ニーチェ自身の発言や思想が、そのような信仰に傾倒している可能性もある
と感じてしまうのではないか。ですがやはりどうも違和感を感じたのです。
あまりにも意図的に結びつけているような感じがしたからです。
「イスラム教」に関する違和感
イスラム教に関する記述はどうかと言いますと、イスラム教の非人道的な側面の例がたくさん
が書かれています。もちろん、そのような非人道的な側面が絶対ないのだと
私が言いたいのではありません。
しかしある側面だけを強調して、そこから彼の言いたい結論に結びつけていると印象を
強く感じたのです。それがなんだか私の中で大きな違和感を感じた部分です。
読者が、読み方を間違えたら、イスラム教=非人道的な宗教というような感じを
受ける可能性もあるのではないか。それは少し怖いことのように感じました。
なぜこうして私が違和感を感じるのかというと、以前読んだイスラム教の本では、
そのような部分とは異なることも書かれてたからだと思います。
だから、こうした一面だけを書いてそれを結論と結びつけることになんとなく違和感を感じました。
ちょっとした私の考え
これらの違和感を持って私が考えたのは、
一つの側面だけではなく別の側面からも考えなければならないのではないか?
また
そのような考えを生み出した背景はなんであるのか?ということを考慮に入れることが
必要ではないか?
ということです。
例えば、ニーチェの話で言えば、
先ほどの引用部分はどういう時代背景があるのか、
またその時代のどのような思想の影響を受けていると考えられるのか、
ニーチェの引用部分はどのような文脈で書かれていたものであるのか
ということも頭に入れておかなければ、正確なことが判断できなのではないかとも思います。
ニーチェが生きていた時代には当たり前にまかり通っていたことが、
私たちの時代では差別的で容認できないことになっていることもあるからです。
例えば、ニーチェの文の中には男女差別と思われる文章もありました。
それだからと言って、ニーチェの思想やその他の意見を否定する理由にはなりません。
なぜなら、その時代は今ほど男女平等という概念が確立されていない時代背景かもしれない。
だとすると、そのような文が出てきても、その時代であれば仕方ないことなのかもしれないからです。
ピンカーの側に立ってみる
こうして批判的なことを書いてみましたが、著者であるピンカー側に立って考える必要が
あるかもしれません。
そのように、ピンカー視点に立つと、ニーチェ、イスラム教のことを一面的な書き方をして
論じてしまうのも、致し方ないことなのかもしれません。
ニーチェ、イスラム教の別の側面があることはおそらく知の巨人なら知っていることでしょう。
ですが、ページ数が限られた(読者が読める量といったほうがいいかもですが)中で、
自分の考えを書かねばならない。だとすると、自分の主張とつながる部分をピックアップして書くこと
は仕方のないことかもしれません。
また、色々と書くことで、論点が見えずらくるということもあると思います。
人は、あれこれと言われるより、断言される方が納得感が増すというのをどこかでみた気がします。
ほとんどのことが不確かな要素、グレーな部分なことばかりである。けれども、それを事細かに書いて
いたら、断言できなあやふやな文章になってしまう。そして、その結果何が言いたいのか
相手に伝わらなければ本末転倒かもしれません。
だからあえて言い切ることによって、読者にわかりやすくしたということもあるでしょう。
そう思うと、読者に自分の考えをわかりやすく伝えるために必要なテクニックということ
になるのかもしれません。
読者側の力量が問われる
だとすると、これは読者側にも力量が問われるなと感じました。
どういうことかというと、もしも純粋無垢にこの本を信じていたら、
もしかするとニーチェのことをナチズム信仰の思想家と思ってしまうかもしれない。
また、ニーチェはナチズム信仰の人間だと信じている人がいて、
これを読んで、やっぱりそうじゃんと、自分の考えの正しさを深める道具になってしまう
かもしれない。もしもそうだとすると、少し怖いなと感じました。
だからこそ、読者側にも力量が必要なのかもしれないなと思いました。
例えば、これってなんだか違和感と思うようなことだとか、
これって本当に正しいのかしらとか、どこかで立ち止まることも必要であるように思います。
だとすると、
私たちがすべきことはどういうことなのか?
それは、いろんな本を読んでみるということなのだと思います。
私自身、ニーチェの違和感は、結局昔にニーチェに関する本を読んでいたから感じたことです。
イスラム教のことも同様です。
自分の前に立ち現れている情報を多面的に見つめることが必要なのかなと。
またそれを前提として、著者が本を書いていることもあるのだろうから、
そうなると本を読むことは非常に奥深いものでもあるなと思います。
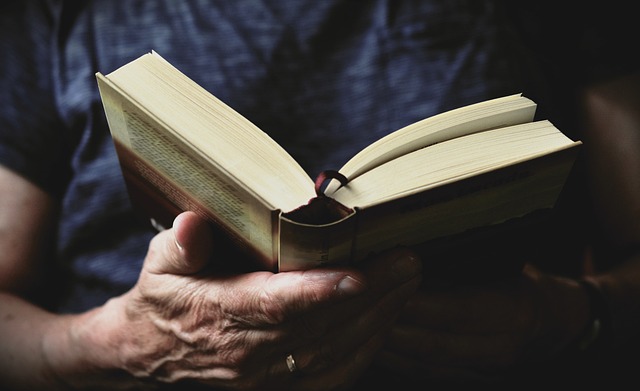



コメント