前回に引き続き、批判的思考について考えてみたいと思います。
今回は『子供が教育を選ぶ時代へ 野本響子』から批判的思考について学んでみたいと思います。
どんな本なのか軽くご紹介
「子供が教育を選ぶ時代へ」はどのようのような本であるか、簡単にご紹介てみたいと思います。
この本は舞台が「マレーシア」です。著者のお子さんが日本の小学校に馴染めない、
そこでマレーシアに行きます。そして、マレーシアの教育の多様性に驚かされたと言います。
そのような著者がマレーシアの学校の在り方などを通して、「教育の選択肢」を紹介している本です。
その中の「第3章「四つのC」を現場ではどう教えているか」で批判的思考クリティカルシンキングが
取り上げられていました。
そこで学んだこと、そしてそこから私がやったことついて書いてみたいと思います。
改めて批判的思考の重要性について
前回も批判的思考の重要性について自分なりの考えなどを書いてみました。
前回の記事は↓
教育のあり方を少しみてみると
今回は、本書、地域としては「マレーシア」から少し考えてみたいと思います。
本書では教育の大きなあり方として、「21世紀型」「従来型」そして「その折衷型」があると
書かれていました。
従来型は、教科書と黒板を使って知識を教える「アジアの伝統的な教育」だそうです。
つまり私たちが公教育のスタイルですね。
21世紀型とは新しい教育で、代表的なものが国際バカロレアだそうです。
従来型が、「教わる教育」、受動型の教育だとすると、
21世紀型は「考える教育」、能動型の教育という個人的なイメージで捉えています。
その新しい教育、能動的な教育の特徴として、
四つのC、
「Communication(コミュニケーション)」「Collaboration(協働)」
「Creativity(創造)」「Critical thinking(批判的思考)」
を教えていると言います。
このように教育の軸の一つとして批判的思考が組み込まれているのです。
どうして四つのCが必要なのか?
ではどうして四つのCが新しい教育、21世紀型の教育に必要なのでしょうか?
本書のその答えが、ユヴァル・ノア・ハラリさんの21Lessomから引用から書かれています。
多くの教育の専門家は、学校は方針を転換し「四つのC」、(上記記載のため省略)を教えるべきだ
と主張している。より一般的にいうと、学校は専門的な技能に重点を置かず、
汎用性のある生活技能を重視するべきだという。
なかでも最も重要なのは、変化に対処し、新しいことを学び、馴染みのない状況下でも
心の安定を守る能力になるだろう。
とあります。
汎用性のある生活技能。これは重要な視点のような気がします。
従来型の教育では、受動型で、いわゆる詰め込み型の教育になりがちです。
そのため、汎用性があるかと言われると、なかなか難しい側面があると考えます。
例えば、歴史の年号を覚えたからといって、別の何かに汎用できるかは、それ単体では意味をなさない
ではないでしょうか。
また今がとにかく変化が激しい時代と言われており、それに対応するには、年号を覚えているよりも、
もしかしたら、それをどのように調べるのか、どのように活用できるのかというような視点の方が
問われている可能性があります。
世界の教育で取り入れられている批判的思考
前回の記事と今回にわたり、二冊の教育の本で「批判的思考」について書かれてありました。
その二冊の教育の本が異なる国、
前回は「フィンランド」、西洋地域、今回は「マレーシア」東南アジア地域というように、
文化圏が異なる国の教育でも、「批判的思考」が注目されています。
たかだかN=2だけで判断するのは、それこそ根拠に欠けるかもしれませんが、
私の直感が、重要な考え方ではないかといっているのです。
(グロックに調べてもらったところ、やはり欧州、アジア、オーストラリア、アメリカなどの教育でも
取り入れられているというような回答がありました。具体的な文献資料なども提示してくれたので、
やはり世界でも重視さ
れているといってもいいのだと思います。)
このようなことから、私は四つのC、今回は特に批判的思考、が重要な考え方なのではないか
と思いました。
批判的思考についてみてみる
では21世紀型教育をしている国際バカロレアの「ディプロマ・プログラム」の批判的思考を
どのように学んでいるか、本書をもとに見てみたいと思います。
(本書では批判的思考を主にクリティカルシンキングと書かれているので
クリティカルシンキングとここからは表記していこうと思います。)
改めてクリティカルシンキングとはどのようなものか。
本書では
ある物事について「本当にそうかな?」「なぜだろうか?」とさまざまな角度から
検証・比較・分析し、考えを深める方法論のことです。
「正解」に飛びつきたくなった時に、一瞬、判断を保留するクセをつけることでもあります。
p96-97
多角的視点と検証、比較、分析という科学的なアプローチ、そして、判断の保留というのが
重要なポイントだと思います。
実際にどのような授業が行われているか
本書によると、
バイアスや誤謬、テクニックを学び、実際の記事を分析
分析するステップは
1、目的は何か
2、ソースは何か
3、メディはどういう立ち位置か
4、バイアスを生んでいないか
ということでした。
さらに注意するバイアスは
擬人化
曖昧な言葉
感情的な言葉
ユーフェミズム(婉曲表現)
センサーシップ
というものだということでした。
詳しくは本書を見てもらうことが必要ですが、今あげたこと、一つの記事について
「検証、比較、分析」を一つ一つ見ていくという作業になるのだと思います。
また、バイアスについても、学んでいるというのはとても興味深いなと思いました。
バイアスは人間であれば誰しもが持ちうるものであり、それらは変化が激しい世の中であっても、
きっとあり続けるものでしょう。それらを知っていることは、そうした変化の中で物事を考える時の
役に立つので知っていて損はないことだと思います。
自分でも実際にやらぬことには、そんな時の助っ人AI!
こうして2回にわたって、色々と批判的思考について書いてきました。論を述べるのは簡単ですが、
実際に自分ができなければ、机上の空論。
ということで、国際バカロレアの方法でやってみたいなと思いました。
しかし、軽い足がかりしかない中で、自分一人でこの方法をやってみて、
それが果たして、どうなのかもわからないままだと何の進展もない。
と頭を悩ましていたところ、そうだ、助っ人A Iがいるじゃないか!
と気がつきAIを使用して取り組むことにしました。
これが非常に良いのです!
どういいのかというと
自分に合った問題を提起してくれる
私が出した答えに対してそれが妥当かを判断してくれる
見逃していたバイアスを教えてくれる
アドバイスをくれる
といったことをしてくれました。
国際バカロレアと比較すれば、全く異なる方法であるとは思うのですが、
これはこれで充実したやり取りができたように思います。
どのようにしたらいいのかという具体的なアイディアももらったので
もう少し深くできるようにしたいと思いました。
そして具体的にどのようなことをしたのか、ブログで書いてみても面白いかなと思っています。
もしも自分でもやってみたいと思ったら、AIに助けてもらうのもいいのかもしれません。
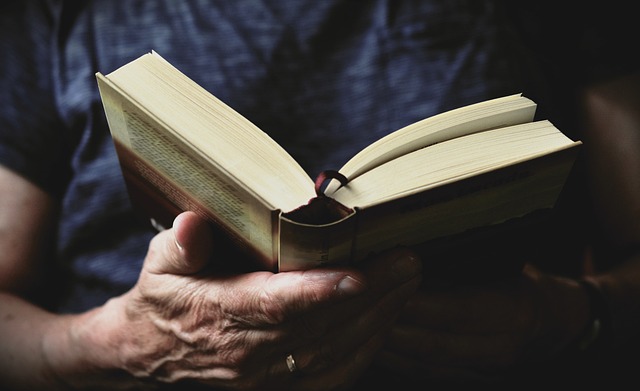


コメント