私にはこんな「能力」がないからうまくかないんだよな、とか、
こんな「能力」が必要なのか、早速本で勉強だとかそういうことを思ったことはありませんか?
私自身時々思うのは「コミュニケーション力」があれば、もう少し人とうまくやっていけるのでは
ないかなと思うことがあります。
でも、ちょっと待って。本当にそうでしょうか?
今回私が読んだ本『「能力」の生きづらさをほぐす 勅使河原真衣』から、
そのような「能力」というもが、実は私たちを縛る大きな幻想だということがわかりました。
そして、本当の「能力」は、どんなものであるのかということを考察しましたので
それについて、2回に渡って書いてみようと思います。
「能力」それが幻と言えるのはなぜ?
「能力」ってそもそも何?「能力」の曖昧さ。
私たちは「能力」という言葉をよく使うし、「能力」というものが会社であれば
何かしら判断の基準になっていたりします。
そもそも「能力」というのは一体なんでしょうか?
能力とは
1、物事をしとげることのできる力。
2、法律上、一定の事柄について必要とされ、または適当とされる資格。
国語辞書の意味、わかるようなわからないような。
このようななんとなくわかるようなわからないような言葉で私たちは評価されているのです。
本書でも例が取り上げられていましたが、こちらの会社ではこの人は能力がないとみなされたが、
別の会社では同じ人はとても能力があるとみなされる。同一人物なのに180度真逆の評価。
こんなことがどうして起こるのでしょうか?
それはその会社の思っている「能力」というものが曖昧であるからではないでしょうか?
「能力」の所有化と万能感
上記の例で、環境が変われば評価が変わる。環境によって「能力」は良いものとも悪いものとも思われる。ケースバイケースのものです。
そのようなあやふやなものにもかかわらず、私たちはどこかでその能力を個人が持っている、
本書の言葉を借りれば、個人の中に臓器のように、存在して力を発揮しているものだと
思いがちです。これさえあれば万能だという「能力」があると思いがちです。
しかし実際はそのようなことは、先ほどの例からもわかるように、ないのだと思います。
つまり、「能力」というのは、万能な無敵な力ではなく、その環境によって変わってくるもので
あると言えるのではないでしょうか?
そんなお前も幻想だったのか!
そのようなことから、「能力」というのは、私たちが勝手に作り上げている幻想に
過ぎないのではないかということなのです。
そのように考えると、現在「能力」を崇め奉るような「能力主義」的な発想が存在しています。
しかし幻想に過ぎないし、ましてはそのような考え方に偏りすぎることは非常に危険なこと
だと思います。
余談ですが、私は以前のブログで、虚構や幻想に過ぎないということを書いています。
それは時に人の心を和らげる考えであるようにも思いますが、しかしそれと同時に
自分たちが作り上げた幻想の世界で、違和感なくというか疑問も持たずに進めていること、
もしくはその疑問や違和感さえも許容し進めていることに、不思議さと、驚きと、なんとも言えない
気持ちです。まだまだ私たちは、そのようなふわふわとした概念のもとに、
それが正しい?あるべきものとして進んでいることがたくさんあるのだろうと
思うと少し怖さも感じたりします。
そんな「能力」を実装しなければならないのか?
そんな幻想なものを、「実装しなければ」というように言われているように感じます。
だからこそ、「能力開発」や「自己啓発」というようなビジネスが成り立っているのだとも思います。
だけれども、その環境によってどうにでも変わってしまう「能力」を、簡単に内臓のように所有し、
なお、それを万能だと信じて実装することが求められることに、どこか違和感はないでしょうか?
そもそも実装できるのか、さらに言えば、そもそも実装しなくてはいけないものなのか?
そのような疑問が湧いてきます。
次回は・・・
今回は少しパンチの効いたことを書いたかもしれません。
そんなことを言ったって、世の中の流れ、風潮はそうなんだということも理解しています。
だからこそ、本書のように「生きづらさをほぐす」という観点で話を書いてくれており、
私たちの違和感に対しての答えを返してくれているのです。
そのような本をもとに、さらに考えてみたいのです。
次回は、世の中の流れといえども「能力」について問題点を考え、そこから、
だったら私たちができることは何かを考えてみたいと思います。
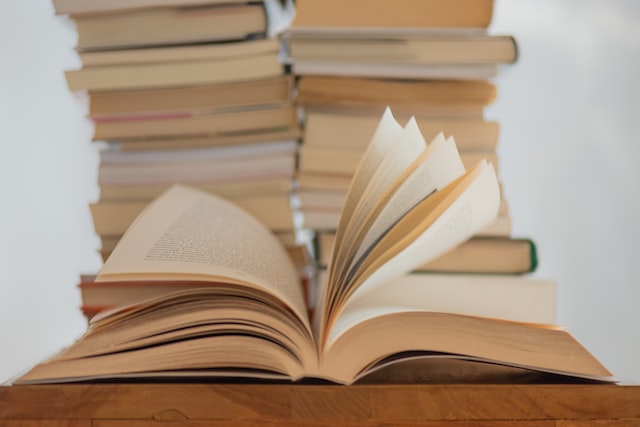




コメント