今回も前回に引き続き『アーモンド』をいう本を読んで、私が時に気になった文から、
感じたことを書いてみようと思います。
『アーモンド』に関する簡単なあらすじは前回のブログに書いたので
そちらを参考にしていただければと思います。
印象的な言葉
私が印象を受けたのは、主人公であるユンジェが、友人のゴニを針金という不良から救おう
としようする最後のシーンで書かれていた言葉です。
遠いければ遠いでできることはないと言って背を向け、
近ければ近いで恐怖と不安があまりにも大きいと言って誰も立ち上がらなかった。
ほとんどの人が、感じても行動せず、共感するといいながら簡単に忘れた。
感じる、共感するというけれど、僕が思うに、それは本物ではなかった。
僕はそんなふうにいきたくはなかった。p245
これは、ユンジェの気持ちである。
彼は恐怖を知らない、恐れをしらない、感情を持たない人として描かれています。
そしてこれがそんな彼の言葉なのです。
自分のことではとハッとさせられる
これを読んで私はかなりドキッとさせられました。
まさに私自身のことではないか、自分への描写ではないかと思ったからです。
私はどちらかというと感情が揺さぶれやすく、共感しやすい性格だと自分のこと考えています。
そして、もしもユンジェのお母さんやおばあちゃんの事件に自分が遭遇していたら、
周りの人同様に、何もできずに立ち上がることはできないだろうし、
ある一定に期間が過ぎると、そのことも忘れていくのかもしれない。
だから、ユンジェの言う、感じる、共感するというけれど、のという人に当てはまっている
と思います。
「普通である」が正しいのか?
そこから考えたのは「普通である」ということが果たして正しいのか?ということです。
正しいというのは少し語弊がありますね。もう少し分解して、「正しい」の意味を考えてみると、
多くの場合、大多数の意見はそれが正しいとか正しくないとか良いとか悪いとかに関わらず、
大きな力となって、動きだします。そしてそれが、あたかも正論=正しさのようになってしまう。
そういう大対数という点で「正しさ」ということを意味しています。
前回見たように、本書では「普通である」ということが重要であるかのように描かれています。
それは「普通である」ということがマジョリティ側となることを意味しており、
マジョリティ側は多いという面で、圧倒的な力を有している。
圧倒的な力があるからこそ、守れているような感覚を持てる。
そして、マイノリティ側を言い方が難しいですが、卑下したり、見下したりすることで、
マイノリティが正しいように見せている。
しかし、それが本当に正しい力であるのか?ただただ数の力というだけではないのか?
そんなことを私たちに突きつけているような気がするのです。
そういう意味において、ユンジェの言葉である「本物ではなかった」という言葉に凝縮されている
のではないかと思うのです。
その大多数って本物なの?って。それが正しいのなら、僕はそうはなりたくないという強い意志。
「普通である」ということのアンチテーゼのような気がしました。
私たちがやっている「普通である」ための行動を考えてみる
もう少しこの本に則ってそれを考えてみたいと思います。
この本では何が「普通である」かというと、感情を持っている人ということになるかと思います。
しかしユンジェは感情を持っていない。だから、それがない人=普通ではないということになる
と思います。
では「普通である」ために私たちがやっていることはどんなことがあるでしょうか?
「普通である」とする私たちは、空気を読んで思ってもないことを言ったり、
笑顔を向けたりとすることがあります。それをユンジェはどういうことか理解できないような
描写があります。これも特徴的な場面だと思います。
普通であることは、周りの空気を読んで、周りの人々の脅威にならぬようにと、
そのような対処をとることがあります。それは集団生活をする上で、必要なことでもあると思います。
ですが、ユンジェの視点で見ると、それは嘘ばかりで、本物ではないというふうに見えるのでは
ないでしょうか?理解できないということですよね。
これらは「普通である」という人々が生きる上で必要な感覚であるという側面もあると思います。
しかし、私たちが当たり前と思っている感覚とは異なる視点から、みることによって、
この当たり前の感覚に、当たり前ではないという視点を入れることで、多くを見渡せるのではないか。
ましては、「普通」ではない人々を卑下したり、見下したりすることが、どれだけ間違っているか
ということも教えられたように感じます。
まとめ
こうして書いていくと、感情がない方がいいとか、感情を持つことはいけないことなのか
ということが言いたいのではありません。
そうした、マイノリティと言われる人の視点を持って、マジョリティ側を除いてみる。
そしてそこからわかったことをどう自分の中で解釈し、どう自分の中に吸収していくのか?
このままマジョリティ側だけの視点で生きていくのではなく、違う視点を持つことで、
少し見方が変わるのではないかということです。
もしも、この考えが有効であるとしたならば、韓国や日本の中にある、「普通である」
ということを重んじ、それを得ることにばかり必死になっているのは重要ではないのかもしれない
とも感じました。
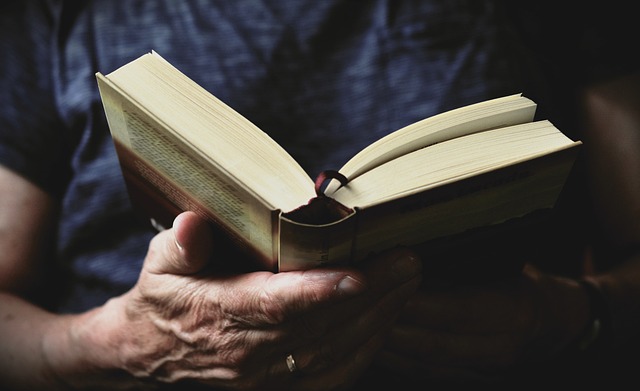


コメント