前回、私が読んだ本『「能力」の生きづらさをほぐす 勅使河原真衣』から
「能力」が幻想であるということを知り、そのことについて書いてみました。
ではその幻想である「能力」というものの問題点と思うこと、
そしていわゆる「能力」というやつは、無理矢理装備するものではないのでは、というところから
ではどうやって身につくものなのか私なりの考えを書いてみようと思います。
幻想である「能力」の問題点ではないかと思うこと
前回、「能力」というのは、絶対的にあるものではなく、環境によって変わってくるもの。
だから私たちがいくら追い求めてもそれがその環境では、「能力」と言われることもあれば、
そうでないということもありうる。そのようなことから、幻想だよねということを知りました。
そのような幻想である「能力」ですが、多くの人に支持され、そして求められている。
これって問題になることもあるよねと感じました。
ではどんな問題点があるのか2点あげてみたいと思います。
それは
謎の「能力」評価で自己否定、個人責任論なりかねない
数値化された能力
です。
謎の「能力」評価で自己否定、個人責任論なりかねない
「能力」を追い求める、また指示するような「能力主義」が多くの場所で存在しています。
そのような能力に依存した「能力主義」というものは、
その場所の独自のルールというかある種、主観とも言える「能力」という基準が存在します。
だからこそ、絶対的な「能力」評価でないにも関わらず、「能力」があるなしという判断になる。
そして最悪の場合は「こいつは何もできない」などと個人を否定になる場合があります。
またその環境に合う「能力」を持ち合わせていないとみなされた場合、「能力」を持っていない、
持とうとしないことで、「個人責任論」になってしまうということが起きる可能性があります。
この部署では、コミュニケーション力が足りないとみなされたら、そんなの自分でなんとか学んで習得できるだろ、学んでいない君が悪いんだというような議論になりかねません。
ここの問題は、「能力」を簡単に装備できると思っていること、
また環境によってその「能力」と言われるものが、良いという評価になったり、
悪いという評価になったりしてしまうということです。
そんな絶対的でないものを追い求めている危うさ、怖さがあると思います。
数値化された能力
先ほど曖昧だと書きましたが、本書にも例がありましたが、それを数値化するというものがあります。
人材開発業界が能力を数値化するということを行っているとあります。
それらのテストを会社で受けたことがある人もいるのではないでしょうか?
もちろん自分にどのような傾向があるのかということを数値化して知れれば
自分のことを知る手掛かりになると思います。ですが、これを過度に信じすぎること、
そもそも幻想である「能力」を数値化したり、科学的根拠というような形で無理やり数値化して
表そうとする、なんとなく違和感を感じませんか。
「能力」とは環境や相手あって浮かび上がるようなもののような気もします。
それを無理やり数値化し、そしてそれを重視することもまた違和感を感じます。
ここで、私が考える問題点とは、数値化することが、難しのではないかという事柄を数値化し、
(科学的な根拠など何かしらあるのかもしれませんが)そして、環境、相手あってのものを、
その数値だけで何かしら判断するということに少し怖さを感じるのです。
本当の「能力」は、相手を思う心から湧き上がる
ということで、「能力」というものの問題点と思われることを書いてみました。
では「能力」というのは、実装するのではないのだとすると、どのように得られるものでしょうか?
私は「相手を思う心」そこから湧き上がるものではないかと思っています。
本書の一文
「私とあなた、という関係性の中で生み出される、
生み出そうと思われる何かしらの気持ちこそが重要なのだということなのかもしれない。」
とあります。
多くの「能力」と言われるものは、人と人の間で必要となるもの。
例えばコミュニケーション能力とは、相手の言葉なりアクションなりが相手にうまく伝わること
だとすると、これは相手なしにはできないものです。それを、how to本に書かれていることを、
いくら装備したとしても、相手もそれに呼応する、気を合わせる、というかそのような力がないと
コミュニケーションは成立しないものだと思います。
だとするとそれらはその場にいる人と人とが互いに何かしらの思いがあって成立するもの。
目の前の相手を思い、どう関わりたいかという心から湧き上がる力ではないか。
このように「能力」というのは、実装するというよりは、その相手を思って行う力なのでは
ないかと思うわけです。
私ができること、やりたいこと
これらのことを踏まえて、過度な「能力」主義に陥らないこと。またそのような場に自分がいたとして、自分自身を責めるのではなく、客観的にみて、その環境のあり方がどうであるかということを俯瞰する必要性があると思います。
そこから色々な「能力」というものを手に入れようとするではなく、私と相手の間に何が必要であるのかということを見てみるということが必要だなと思います。またそうしたものは、評価されにくい、つまり数値化されないため、人にわかりずらいということがあります。ですが、実際数値化されるようなわかりやすいものよりも、こうした見えない力こそが重要であるような気がします。だからこそ、それを意識する。みようとするということも重要だと思います。
また「能力」のせいにして、人を判断するのではなく、「どんな環境なら力を発揮できるか」をいう視点をもちか、環境全体として考えていく必要があると思います。
もっとシンプルで人間らしいもの――相手を思う心から湧き上がる力。それこそが「能力」と言えるのかもしれません。
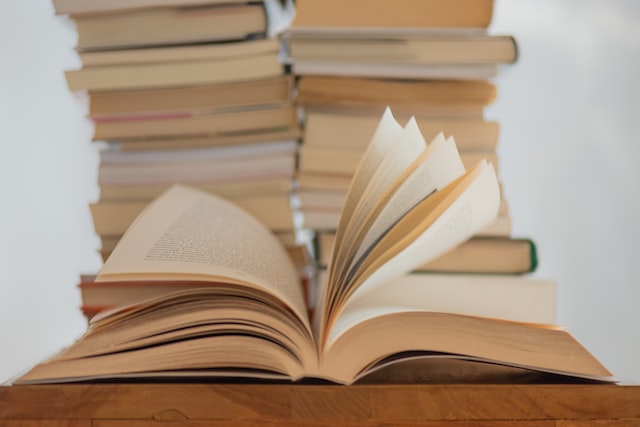


コメント